「自分の物件を自分で管理したい」
そんな想いから始まる“賃貸の自主管理”。
不動産管理会社に委託せず、大家自身が入居者募集や契約対応、クレーム処理まで一貫して行うスタイルです。
コストを抑えられる一方で、トラブルや法律対応には注意が必要です。本記事では、自主管理で賃貸運用を行うメリット・デメリット、そして契約時に気をつけたいポイントまで解説します。
自主管理とは?賃貸編の定義
賃貸物件の自主管理とは、大家(オーナー)が管理会社を介さずに、直接すべての管理業務を行うことを指します。
主な自主管理業務一覧
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 入居者募集 | SUUMO・アットホーム等に掲載、または知人紹介 |
| 契約締結 | 賃貸借契約書の作成・署名捺印 |
| 家賃管理 | 振込確認・滞納督促 |
| クレーム対応 | 設備故障・騒音などのトラブル対応 |
| 退去手続き | 退去立会い・原状回復手配 |
自主管理のメリット
1. 管理費を削減できる
通常、管理会社へ支払う手数料は家賃の3〜5%前後。これがなくなれば、収益率は確実に上がります。
2. 入居者の状況を把握しやすい
直接やり取りすることで、入居者の人柄や生活スタイルを把握しやすくなり、トラブル回避に役立ちます。
3. 柔軟な対応が可能
例えば、「数日遅れの家賃は許容する」「DIYを許す」など、オーナーの裁量で判断できます。
自主管理のデメリット
1. 対応時間と労力が必要
夜中のトラブルや日中の電話対応など、日常生活に支障をきたす可能性もあります。
2. 法的なリスク管理が必要
契約書の不備、敷金精算トラブル、原状回復の判断など、法令に基づいた対応が求められます。
3. クレーム対応が精神的に負担
設備トラブル、隣人との騒音問題などに対して、冷静かつ迅速な対応が必要です。
賃貸契約書の注意点
自主管理の場合、契約書の重要性はさらに高まります。特に以下の点を押さえましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 原状回復 | 国交省ガイドラインに準拠した記載を推奨 |
| 滞納時の対応 | 期限・催促回数・解除条項を明記 |
| 中途解約 | 解約予告の期間(例:1ヶ月前) |
| 特約事項 | 禁煙・DIY可否など細かく記載 |
💡 法律の専門知識が不安な場合は、契約書のひな形を使うか、不動産の士業にスポット相談を行うのも手です。
自主管理でよくあるトラブルと対策
| トラブル例 | 対策方法 |
|---|---|
| 家賃滞納 | 保証会社の利用+明確な契約書 |
| 騒音・迷惑行為 | 近隣への配慮を促す条文を記載 |
| 設備不良対応遅れ | 故障時の連絡手段を明示+迅速な手配 |
| 退去時の修繕費トラブル | 写真付きの入居時チェックシート活用 |
自主管理向きの物件とは?
- 戸建てや小規模アパート
- 入居者が長期化しやすい立地
- 設備が比較的シンプルな物件
これらの条件がそろっていると、トラブルの頻度も抑えやすく、自主管理に向いているといえます。
自主管理が不安なときの対応策
- 一部業務のみ管理会社へ委託する「部分委託」を活用
- 家賃保証会社を導入
- トラブル時に専門家へスポット相談(司法書士、不動産コンサル等)
まとめ
賃貸物件を自主管理することで、収益性の向上や入居者との関係性構築といったメリットが得られます。一方、手間や法的対応の難しさというデメリットもあるため、物件の規模や自身のライフスタイルに応じて判断が必要です。
「自分の手で資産を育てる」
そんな感覚を持ちたい方に、自主管理は一つの選択肢となるでしょう。








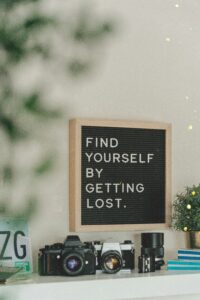
コメント